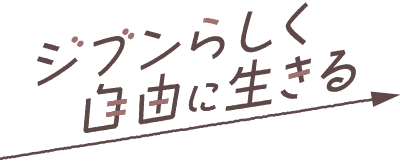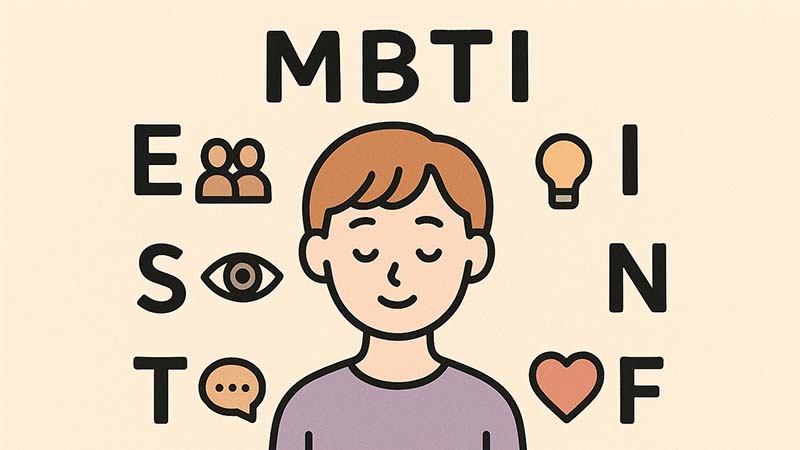MBTIとの出会いとハマり始めた頃
昔から性格診断というジャンルに惹かれ、ネットで見つけては様々な診断を試していた。
そんな中で出会ったのがMBTI。日本でもブームの波が来ていた時期だったこともあり、自分でも驚くほど深くのめり込んでいった。
遡ってみると、MBTIにハマり始めたのは2024年に入る頃。気がつけば1年以上、毎日のようにMBTIについて調べ、考察をブログに書き留める日々を送っていた。
公式の学びと見えてきた限界
MBTIの理解を深めようと、関連書籍を読み、公式セッションも経験した。
その結果、最終的な自己診断では「ENFP」とした。
最初は「自分を客観視できる術を手に入れた」という実感があり、その枠に当てはまったことに一種の安心感さえ覚えた。
だが、時間が経つにつれ、私はその「枠」からこぼれ落ちる自分の存在に気づき始めた。ENFPというタイプだけでは説明できない自分の思考・行動のクセや、環境によって変わる側面が確かにあった。
そして、他人を観察するうちに、その感覚はさらに強まった。
MBTIというモデルに感じた違和感
公式のMBTIは「生まれながらにして変わらない心理的傾向」を測るモデルだとされている。だが私は、この前提そのものに疑問を感じている。
たとえば、「S型は連想ゲームで枠から外れた発想をしない」や、「T型は物事を現実ベースで考える」といった説明があるが、そもそもこのような傾向は環境や経験による正解によって大きく左右されるのではないか?
生まれたときから“正論パンチ”をかます子どもも、”やたら共感してくる”子どもも、中々いない。
思考のパターンは、成長の過程や育った文化によって生きていくと共に形作られる側面が強い。にもかかわらず、MBTIが「変わらない本質」としてそれらを分類しようとするのは、正直言って乱暴にも思える。
さらに言えば、私自身、EとI、FとT、PとJの境界線に常に揺れるタイプだ。
「どちらにも属さない」「どちらにも似ているが、決定的に違う」その曖昧さを、MBTIの型には収めきれなかった。
MBTIは商標登録されたビジネスであり、多くの情報が個人の解釈や書籍に委ねられている点も、構造としての限界を感じさせる。エニアグラムのように、ストレス時の反応や変化への理解が系統立てて定義されていないのも、大きな弱点だと感じた。
MBTIの位置づけと、私の今のスタンス
それでも、私は今もMBTIというジャンルが好きだし、調べることも続けている。ただし、それはあくまでも「娯楽として」だ。
MBTIは、自己探究の“入り口”としては非常に有効だと思う。自分のパターンに気づくきっかけとして、多くの人に役立つだろう。
だが一方で、MBTI一つで「自分とは何者か」を決めつけてしまうには、あまりにも道具としての強度が足りない。
知れば知るほど、MBTIはチープに感じられるようになった。
人間の複雑さ、変化し続ける思考や感情をたった4つのアルファベットに閉じ込めるには、あまりにも浅すぎる。
それが、1年追い続けて私が出した結論だ。